
建築・建設業界では、日々の業務が複雑化・多様化する中で、「契約」にまつわる課題が見過ごされがちです。「いつも通り」「口約束でも大丈夫」「紙で残っているから安心」——そうした慣習的な対応が、実はトラブルの原因や非効率の温床になっているケースも少なくありません。
近年では、建設業法に基づく書面契約の義務はもちろん、電子契約の導入や契約フローの“見える化”といった流れが急速に進んでいます。特に顧客対応や外注管理の面で、「契約が整っていること」自体が信頼や選ばれる理由になる場面も増えてきました。
こうした変化の波にどう向き合い、どこから手をつけていけばよいのでしょうか?
本記事では、駐車場手配代行BPOサービス「JESUS」を運営するランドマークが、建築・建設業界の方からよくいただくお声を参考に、現場と契約の“見直しポイント”を整理し、契約DXのヒントをご紹介します。
目次

契約書が存在していても、実際の業務では「なんとなく」の合意や「過去と同じ条件で」といった曖昧な取り決めが見過ごされがちです。とくに建築・建設業界では、業務の流動性や関係性の長さから、形式より“慣習”が優先されることも少なくありません。
しかし、こうした曖昧さが小さな食い違いやトラブルの火種となり、現場や管理部門の負担を増やしているのも事実です。
この章では、曖昧な合意がどのようなリスクを生み出しているのかを見ていきます。
一つ一つ見ていきましょう。
「言った・言わない」「確認してなかった」——これは現場でよく聞くフレーズです。実際に国土交通省の報告では、下請取引に関する国土交通省の調査によれば、知事許可の一般建設業では、約60%が不適切な契約方法をとり(例:書面化されていない)、そのうち18.8%が口頭やメモ等で交わされているというデータもあり、契約書の不備が依然として根深いことが分かります。
現場のスピード感や人間関係の信頼に頼って業務を進めてしまう傾向がある一方で、こうした非公式なやりとりが後々のトラブルを招く温床になっているケースは少なくありません。
参考資料:国土交通省『令和2年度下請取引等実態調査の結果について』、建築魂『建設業、約9割が下請けとの契約不適正…メモ・口頭による契約目立つ』
「一応話はしてあるから」「内容はメールで送ったから大丈夫」など、“契約したつもり”で業務を進めた結果、納品内容や金額、支払い条件をめぐる認識のズレが後になって顕在化する——これは非常に多いトラブルのパターンです。
とくに業務範囲があいまいな作業(例:現場清掃や臨時の駐車場手配など)では、文書化されないことで「やる・やらない」の解釈が分かれ、現場が混乱するケースも見られます。
建設業法では、元請・下請間での契約書面化が義務付けられています。にもかかわらず、契約書の未作成や不備が生じる背景には、「書類作成の手間」や「相手に言いづらい」など、現場ならではの実務的ハードルが存在します。
また、作成したとしても署名・捺印まで進まずに放置されたり、最新版が共有されていないまま業務が進行している事例も見られ、いかに“契約の見える化”が遅れているかが浮き彫りになります。
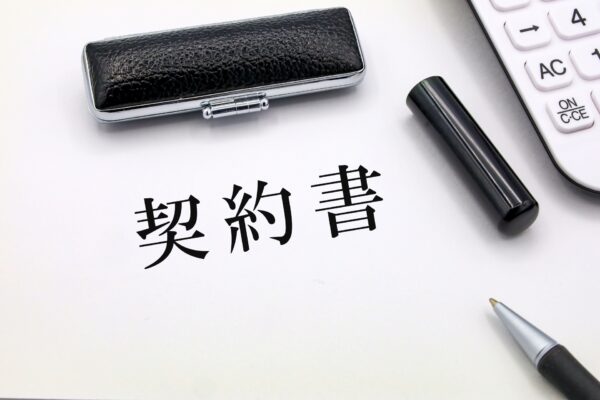
契約書そのものは存在していても、「どこにあるか分からない」「過去のファイルに埋もれている」といった状況が、建築・建設業界では当たり前のように見られます。また、形式上は整っていても、内容の更新や共有ができていないことで、現場が正確な条件を把握できずに進行してしまうケースも後を絶ちません。
この章では、こうした現状を踏まえ、「なぜ今あらためて契約を見直す必要があるのか」について、業界の変化とともに整理します。
上から整理していきます。
業界全体が長らく「紙で運用することが当たり前」とされてきた背景には、相手先との信頼やアナログな慣習が根強く残っているからです。しかし、災害時の書類消失や、保管スペースの限界、紛失・検索性の課題といったリスクは、徐々に無視できないものとなっています。
また、書類の作成・印刷・製本・郵送・押印といった一連のプロセスには、一定の人手と時間を要するため、業務負担が増す一因にもなっています。業務のスピード化やコスト見直しが求められる中、こうした運用の見直しを検討する企業が増えているのは自然な流れと言えるでしょう。
「契約書はちゃんと作った、あとは倉庫の奥」という時代では、現場の判断や顧客対応に必要な情報が取り出せず、トラブル時に後手を踏む原因になります。今求められているのは、契約書の作成だけでなく、その“活用”や“共有”の視点です。
たとえば、電子契約であれば、内容の検索・履歴管理・進捗確認が容易で、現場・経理・営業が同じ情報をもとに動ける体制が整います。これは単なるペーパーレス化ではなく、“業務の見える化”そのものに直結する改革でもあります。
建設業法による契約書面化の義務はもちろん重要ですが、それ以上に、「現場の不安を減らし、会社の意思決定を加速する」という観点での契約活用が求められています。誰が、何を、いつまでに、いくらで、どのように——という業務の基本情報が契約で明確化されていれば、現場は迷わず動けますし、責任の所在も明確になります。
また、契約書が“経営判断の道具”として機能することで、外注管理や顧客対応にも安定感が生まれ、信頼性の高い事業運営へとつながっていきます。

建築・建設業界では、契約の電子化に取り組む動きが進む一方で、紙中心の運用もまだ根強く残っています。
この章では、電子契約の普及状況とその背景を整理します。
それぞれ整理していきます。
建設業界の電子契約導入率は、まだ約3割台とされ、多くの企業が導入に踏み切れていない状況にあります。この背景には、支配的な紙文化への慣れや、現場ごとの判断・手続きが絡む複雑さが影響しています。
前章で既に口約束の実態を共有したように、形にこだわらず「業務の進めやすさ」を優先する業界の傾向が色濃く表れています。
参考資料:PR TIMES『つなぐマーケティング電子契約サービスを導入している企業は4割未満!電子契約の認知度と導入率に関する調査結果【2022年版】 』
一方、先進的な地方自治体では公共工事の契約における電子化が進んでおり、愛知県豊田市では契約件数の97.8%が電子化されています。
このように、公共の信頼性確保や効率化を目的とした電子化の成功事例も存在し、産官連携の可能性を示唆しています。
参考資料:PR TIMES『愛知県豊田市が建設関係の電子契約率約98%を達成【GMOグローバルサイン・HD】 』
なぜ建設業で電子契約が進まないのでしょうか?それは以下の要因が複雑に絡んでいるからです:
1.現場主導の業務フローとの不整合
現場では契約対応より施工が優先されがちで、契約フローに割く時間が確保しにくい。
2.取引先・協力会社の対応状況
特に中小企業や職人レベルでは「紙の方が安心」と感じる声が根強い。
3.慣習・心理的な壁
書類作成・電子署名・進捗共有などが新たな手間に感じられ、踏み切れないケースも多い。
これらによって、導入率は低止まりというより「進行の速度が緩やか」である状況です。

建築・建設業界では依然として紙文化が根強い一方で、電子契約へのシフトは確実に進行中です。
この章では、顧客ニーズの変化や実際の導入メリット、そして移行企業の実例から、なぜ“今”電子化に向かうべきなのかを考えていきます。
一つ一つお伝えします。
ドキュサイン・ジャパンの2022年国内調査によると、電子契約サービスを利用した人のうち約94%が「便利だと感じた」と回答し、そのうち25%が「非常に便利」と感じていると報告されています。
このような高い利便性評価は、建築・建設業界でも顧客からの評価向上や信頼感につながる可能性が高く、「対応スピードが早く、ストレスが少ない会社」として選ばれる理由になります。
参考資料:ドキュサイン・ジャパン『【2021年版】市場調査からみる電子契約/電子署名サービスの現状とニーズ 』
電子契約には、以下のような具体的なメリットがあります:
これにより、従来かかっていた手間・コスト・時間が大幅に削減されます。契約締結にかかる平均期間が「1週間→当日」へ短縮されるなど、実務面での効果も見逃せません。
電子契約を導入した建設会社からは、次のような声が寄せられています:
「業務部門・現場・経営が一つのプラットフォームで動けるようになり、情報の共有がスムーズになった」
「郵送や印紙にかかる費用がなくなり、年間数十万円のコスト削減になった」
「以前より契約のステータスが明確になり、トラブルが減った」
このように、現場負担の軽減・業務効率の向上・コスト削減の3拍子がそろうことで、導入企業の多くが「もっと早く始めればよかった」と語っています。

電子契約の導入において、すべてを一気に切り替えるのはハードルが高いものです。建築・建設業界では、まず身近な契約から段階的に導入する“スモールスタート”が成功の近道になります。
この章では、無理なく始めるための工夫を3つご紹介します。
一つ一つ紹介します。
契約全体を電子化するのではなく、まずは領域を絞るのが効果的です。たとえば:
このように最も負担が少ない領域で効果を検証することで、「実際に使える」実感を得やすく、組織全体の導入の障壁が下がります。
電子契約導入の第一歩は、書式の標準化と承認プロセスの明文化だと言えます。例えば:
これにより、今どの契約が止まっているか・誰の承認待ちかが一目で分かるようになり、管理漏れが減り、現場のストレスも軽減されます。
電子契約は単なるツール導入ではありません。導入を成功させるには、現場・事務・経営が一体となった推進体制が不可欠です。具体的には:
こうした体制を整えることで、部分的な運用から全体的な仕組みへと自然に定着させていくことが可能です。

建築・建設業界では、自社施工だけでなく、さまざまな外部パートナーとの協働が日常的に発生します。とくに駐車場手配や車両管理、警備、清掃といった周辺業務は、工程全体を支える重要な要素でありながら、「契約の抜け漏れ」が起きやすい領域でもあります。
この章では、こうした外注業務こそ、明文化・契約化によって安定性を高めるべき理由と、信頼できるBPO活用への第一歩をご紹介します。
一つ一つ紹介します。
「小さな業務だから契約はいらない」——そう思っていませんか?たとえば、現場近隣の駐車場手配や車両の搬入・誘導といった業務でも、手配の遅れや情報の齟齬が、工程全体に影響を及ぼすことがあります。
こうした業務は外注化する際にも、「どこまでが対応範囲か」「変更時の連絡は誰が行うか」といった具体的な取り決めを文書で残すことが、トラブル防止と品質維持のポイントです。
BPO(業務委託)を活用する際に重要なのは、単なる「業務の外注」ではなく、「契約をベースにした運用体制」を整えることです。特に建築・建設業界では、委託業務の内容が現場ごとに変わることが多く、仕様が曖昧なままだと、委託先との認識にズレが生じがちです。
たとえば駐車場手配であれば、「現地調査の有無」「手配範囲」「天候や工期変更時の対応」など、業務フローの想定と条件を明文化しておくことで、業者任せの属人的対応から脱却できます。
安心して任せられる体制とは、つまり「何をどこまで依頼し、その結果をどう共有するか」が契約で整理されている状態です。これにより、業務の属人化を避け、サービス品質のばらつきも抑えられます。BPO導入を成功させるには、まずこの視点で「契約の中身」から見直すことがスタートになります。

建築・建設業界では、日々変動する現場事情や多様な関係者との連携の中で、契約の存在が“守るための仕組み”としてますます重要になっています。単なる法律上の義務ではなく、現場の混乱を防ぎ、顧客からの信頼を築き、会社として安定的に成長していくための基盤——それが契約です。
口約束や紙の書類が当たり前だった時代から、今や電子化による迅速かつ確実な契約運用が主流になりつつあります。もちろん、すべてを一度に変える必要はありません。大切なのは、「できるところから変えていく」という姿勢です。
たとえば、駐車場手配や車両管理といった周辺業務も、きちんと契約で定めておくことで、無用な混乱やストレスを防ぐことができます。
本記事では、駐車場手配代行BPOサービス「JESUS」を運営するランドマークが、建築・建設業界の方から寄せられた現場の声をもとに、契約を見直すべき理由と、その具体的な方法について整理してきました。
今後の変化に柔軟に対応し、信頼される事業体制を築いていくためにも、「契約」を“守るための道具”として見直すことが、第一歩となるのではないでしょうか。
もし10万件以上の実績がある、ランドマークの駐車場手配代行のBPOサービス『JESUS』のことをもっと知りたい方は、下記のバナーから詳細をご覧ください。
Archive