
建築・建設業界は深刻な人手不足が続くなか、高齢化や若手の業界離れにより、現場の担い手不足はより一層深刻になっています。そうした背景から、いま多くの企業が外国人労働者の受け入れに注目しています。
すでに多くの現場では、技能実習や特定技能などの在留資格をもった外国人が働いており、「日本人と同じように戦力になっている」と評価する声も増えてきています。一方で、言葉の壁や文化的な違い、制度理解の不足など、受け入れにあたっての課題も見逃せません。
本記事では、駐車場手配代行BPOサービス「JESUS」を運営するランドマークが、建築・建設業界の方からよくいただく現場の声をもとに、外国人労働者を取り巻く現状から制度の最新動向、実際の現場での工夫までを網羅的に整理し、「これからの建設現場に求められるあり方」について、実践的な視点でひも解いていきます。
目次

建築・建設業界では、慢性的な人手不足が大きな経営課題となっています。特に現場作業においては、経験豊富な技能者の高齢化が進む一方、若手の入職は伸び悩み、人材の空白が年々広がっています。これにより、施工スケジュールの遅延や安全リスクの増加といった実務的な影響も無視できない状況です。
この章では、国内の人材不足の実態を「高齢化」「技能者数の推移」「企業の危機感」という3つの視点から整理していきます。
一つ一つ整理していきます。
総務省「労働力調査」をもとにした国土交通省の分析によると、現在の建築・建設業就業者において55歳以上が約36.6%、29歳以下が11.6%を占めており、全産業と比較しても高齢化が顕著です。特に60歳以上の技能者は全体の約25.7%を占め、10年後にはその大半が引退すると見込まれており、技能継承の緊急性が増しています。
業界イメージや労働環境が原因で若年層の参入が難しい中、定年退職を迎えるベテランの穴を埋めきれず、結果として“空白地帯”が生まれているのです。
参照:国土交通省『建設行政に関する最近の話題(令和6年6月)』
国土交通省の資料によると、建設技能労働者の数は1997年の約685万人をピークに減少を続け、現在はピーク時の約70%前後である約483万人(令和5年平均)にまで下落しています。技能労働者数はピーク時約455万人から現在は約304万人にまで減少しており、就職・離職バランスの悪化が続いています。
今後10年間で60歳以上の約3割が引退すると予測されており、このままでは技能継承そのものが途絶える懸念も出ています。政府は「担い手確保・育成策」を進めていますが、即効性が乏しい中で現場は自衛的な対応を迫られています。
参照:国土交通省『建設業における人材確保に向けた取り組みについて(令和6年8月29日)』
「求人を出しても応募がない」「採用してもすぐ辞める」——こうした声が中小建設会社を中心に聞かれます。とくに地方や専門職ほど人材確保が難しく、外国人の受け入れに頼らざるを得ない状況が現実です。
その現実はデータとしても現れており、帝国データバンクの調査では、2024年は人手不足倒産件数が建設・物流業で全体の約40%を占めており、外的圧力が経営にも大きな影響を与えていることが分かります。また、2025年4月時点で「正社員の人手不足を感じている」企業は51.4%、建設・物流業では約70%にものぼるとの調査もあります。
中には「日本人だけで現場をまわすのは、もう限界」という声もあり、外国人労働者の活用は“選択肢”ではなく“必要条件”になりつつあるのです。
参考:
帝国データバンク『2024年度の人手不足倒産過去最多の350件』』

建築・建設業界では人手不足の深刻化に伴い、外国人労働者の活用が重要な選択肢となっています。しかし、その実態や制度の理解にはまだ温度差があるのが現状です。「どのような制度で働いているのか?」「どれくらいのスキルがあるのか?」といった基本情報こそが、受け入れの第一歩になります。
この章では、建築・建設業に従事する外国人労働者の在留資格や制度、そして実際の戦力化の実情について整理していきます。
上から整理していきます。
外国人労働者は複数の在留資格で建設現場に携わっています。厚生労働省によれば、外国人労働者(延人数約230万人)のうち、建設業は、5年前の約7万人から2023年の約14万人と倍増しています。また、パーソル総合研究所と中央大学の共同研究「労働市場の未来推計2035」では、建設業は2018年の約7万人から2023年の約14万人と倍増しており、外国人労働者の活用が進んでいるという報告がされています。
建設支援に特化すると、技能実習生や特定技能、そして高度人材となる「技術・人文知識・国際業務」などが主です。これらの資格には、それぞれ就労可能な業務内容や期間に違いがあります。
参考:
厚生労働省『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)』
パーソル総合研究所『都道府県別に見る外国人労働者の現状』
外国人が建築・建設業で働くにあたり、主に活用されているのが「技能実習」と「特定技能」という2つの在留資格です。両者には以下のような違いがあります。
技能実習
特定技能(1号・2号)
このように、技能実習が「人材育成」に近い制度であるのに対し、特定技能はより「戦力」としての即戦力性が求められる制度です。近年では、実習生から特定技能への移行も進んでおり、長期的な雇用を前提とした制度活用の必要性が高まっています。
「外国人=初心者」といったイメージを持たれることもありますが、実際には、母国での建設業経験がある方や、技能実習で複数年の現場経験を積んだうえで特定技能へ移行している方も多く見受けられます。とくに特定技能で働く人材は、就労前に日本語・技能試験の合格が義務付けられており、一定以上の基礎力と実務理解があることが前提となっています。
また、若く柔軟な外国人スタッフは、最新の建材やデジタル機器にも積極的に順応する傾向があり、「日本人スタッフよりもIT機器に強い」と評価されるケースもあります。業務を通じて日本語力も向上し、数年後には職長補助や新人教育にも関わる存在として期待されている企業もあります。
受け入れ体制とサポート環境が整っていれば、外国人労働者は十分に“即戦力”となり得る存在です。実際、現場の一部では「もはや日本人・外国人の区別なく頼れる戦力」として活躍している例も珍しくありません。

建築・建設業界では、外国人労働者の現場配属が増える中、言語や文化の違い、安全管理体制などに起因する現実的な課題が顕在化するようになっています。これを見過ごすと、現場の連携不足や事故リスクにつながるため、制度や仕組みでカバーする視点が不可欠になります。
この章では、現場で直面しやすい3つの課題と、その向き合い方について整理します。
それぞれ見ていきます。
外国人労働者を受け入れる際、最も顕著に現れる課題が「日本語能力」や「文化背景」の違いです。たとえば日常的な指示や細かな作業内容の伝達が伝わらず、誤解や作業ミスにつながるケースがあります。
ある調査では、外国人労働者を採用しなかった理由として「言葉の壁」が39.2%、「文化・習慣の違い」が19.6%にのぼっており、現場での意思疎通に課題があることが明らかになっています。
参考:厚生労働省労働基準局『令和5年外国人労働者の労働災害発生状況』
技能実習や特定技能の外国人は現場経験が浅かったり、日本の安全ルールに馴染んでいなかったりする場合があります。実際、厚労省のデータでは、建設業における外国人労働者の労災発生率が高いことが指摘されています。
安全教育が不十分だと、本人だけでなく作業全体のリスクが高まるため、言語支援や多言語マニュアルの整備など、教育の仕組み化が求められます。
参照:厚生労働省労働基準局『令和5年外国人労働者の労働災害発生状況』
単なる労力確保ではなく、長期的な戦力として育成する視点が重要です。一部の建設会社では、技能実習から特定技能への移行、そこから日本人と同等の技能習得まで段階的にサポートする取り組みが進んでいます。
特に、協働する職長や先輩が言葉や文化の橋渡し役を担うことで、本人の定着やモチベーション向上につながっている事例もあります。

建築・建設業界における外国人労働者の活用は、「雇って終わり」ではありません。職場に定着し、戦力となってもらうためには、企業としての“受け入れ力”が問われます。
この章では、実際に現場でできる工夫や体制整備のポイントを見ていきます。
一つ一つ見ていきます。
言葉の壁は、現場の安全や効率に直結する問題です。限られた日本語力でも作業できる環境を整える工夫が求められます。
これにより、視覚情報をもとにした指示伝達が可能となり、誤解やストレスを減らすことができます。特に危険作業では、音声よりも視覚情報のほうが効果的です。
「せっかく育ててもすぐに辞めてしまう」——この課題に直面する企業は少なくありません。離職を防ぐには、働きやすさと成長の実感が重要です。
特に「技能が評価されている」「職長も目指せる」と実感できることが、定着率を大きく左右します。
外国人スタッフが加わる現場では、元請・下請・外注をまとめた「チーム全体の共通ルール」が欠かせません。以下のような仕組みをそろえることで、定着率と安全性が大きく向上します。
とくに外注先には、実務ルールや安全基準を「伝えて終わり」ではなく、「共に守る」姿勢を示すことが重要です。周辺業務まで含めて仕組み化すると、現場全体の一体感が高まり、外国人スタッフの定着と安全管理を同時に強化できます。
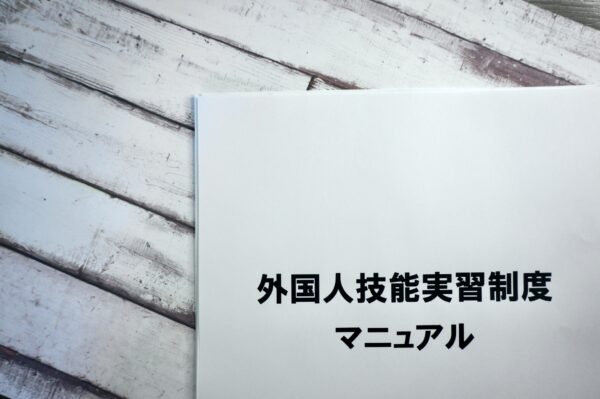
2025年は、外国人材受け入れ制度が大きく転換点を迎えています。なかでも建築・建設分野では、特定技能2号の拡大や助成金メニューの新設など、即戦力を長期的に確保しやすい仕組みづくりが進んでいます。
この章では、最新の制度改正を3つの観点で整理します。
一つ一つ整理します。
2025年4月、建設分野の特定技能は従来の19業務から「土木・建築・設備」の3区分へ再編され、2号対象職種の範囲と能力評価基準が刷新されました。実務経験の証明方法も簡素化され、2号への移行者が増えやすい環境が整っています。
さらに、国土交通省は2025年度末までに2号受入れ上限を2万人へ引き上げる方針を示しており、長期雇用を前提とした人材戦略を立てやすくなりました。
参考:国土交通省『土地・不動産・建設業 お知らせ【特定技能制度(建設分野)】』
厚生労働省は2024年度から「外国人労働者就労環境整備助成コース」を拡充し、社内多言語マニュアルの作成や生活支援体制の整備に最大100万円を助成しています。また、各都道府県では通訳付き安全研修費を補助する独自メニューを創設する動きが広がっています(例:愛知県・福岡県で2025年度開始)。
こうした公的支援を活用すれば、受け入れコストを抑えながら定着率向上を図ることが可能です。
参考:厚生労働省『人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)』
国土交通省は「建設特定技能受入計画ガイドライン」を2025年1月に改正し、
を盛り込みました。負担軽減と質の高い支援を両立する設計に変わりつつあります。さらに、建設業のICT活用補助(地域の守り手事業)では、外国人を含む全作業員へのタブレット貸与経費も対象になり、言語・安全の両面でデジタル化を後押ししています。
参考:国土交通省『建設分野技能実習に関する事業協議会について』

外国人労働者の受け入れを検討・実施する企業としては、「制度の細かい違い」「現場のコミュニケーション」「安全管理」などの疑問が多いと思います。
この章では、建築・建設の現場で実際によく相談される代表的な質問と回答を7つまとめました。
Q1.技能実習生と特定技能1号・2号の違いが分かりにくいです。
A.技能実習は「技能を学ぶこと」が目的で在留期間は最大5年、転職は原則不可です。特定技能1号は「人手不足分野の就労」が目的で最長5年・転職可、2号は在留期限がなく家族帯同も可能です。長期雇用を前提にするなら、1号から2号へ移行できる仕組みを早めに検討すると安心です。
Q2.日本語力が不十分な人に現場ルールをどう伝えれば良いですか?
A.指示を短い文+イラストで示すピクトグラム、動画マニュアル、翻訳アプリを組み合わせる方法が効果的です。日常的に“見せる指示”を行うことで誤解が減り、定着が早まります。
Q3.安全教育は何語で実施すれば良いでしょうか?
A.日本語+母国語資料の併用を推奨します。最初に母国語でポイントを押さえ、現場では日本語で具体指示を出す二段階方式にすると理解度が安定します。
Q4.外国人はすぐ辞めると聞きますが、定着させるコツはありますか?
A.生活面のサポート(住宅・行政手続き)とキャリアパスの提示(例:技能実習→特定技能→班長補佐)が鍵です。自分の成長と生活の安心が両立すれば、離職率は大きく下がります。
Q5.家族帯同を認めると現場運営に影響が出ますか?
A.特定技能2号で家族帯同を許可すると長期定着につながります。生活支援負担は増えますが、代わりに転職リスクが低減し、技能継承も安定します。
Q6.社内に外国人対応の担当者を置くべきでしょうか?
A.はい。窓口が明確だと相談先がはっきりし、現場での小さなトラブルが拡大しにくくなります。人事・現場・通訳を横断した「3者連携体制」を目指すと効果的です。
Q7.外注先にも多言語化を求めるのは負担では?
A.最初に共通フォーマット(電子日報や安全書類)を提示し、「ここまで対応いただければOK」というラインを設けると混乱なく進みます。受け入れ体制を共有することで、外注先との連携品質も向上します。

人手不足が長期化するなか、外国人労働者は建築・建設業にとって欠かせない戦力になりつつあります。制度面では特定技能2号の拡大や助成制度の充実が進み、企業が長期的な雇用戦略を描きやすくなりました。また、現場レベルでは言語支援・安全教育・キャリアパスづくりをセットで行うことで、定着率を高めながら技能継承を加速できます。
要点を整理すると――
1.制度活用の柔軟性
特定技能1号→2号への移行支援を早めに設計し、長く働ける環境をつくることが企業の競争力につながります。
2.共通ルールとデジタル基盤
多言語マニュアルやクラウド共有で「誰が見ても同じ情報」を担保し、ミスやトラブルを減らします。
3.“育てる”視点の徹底
生活支援とキャリア形成を一体で考え、外国人と日本人が同じ目標に向かってスキルアップできる組織風土を醸成します。
こうした取り組みを積み重ねれば、日本人と外国人が協働しながら新しい現場文化をつくり出すことができます。たとえば、駐車場手配をクラウドで一括代行できるサービスを組み込むことで、外注先も含めた全員が同じプラットフォームで情報を共有でき、コミュニケーションロスを大幅に削減できます。これは受け入れ体制づくりの小さくて大きな一歩です。
もし10万件以上の実績がある、クラウドで一括管理も可能なランドマークの駐車場手配代行のBPOサービス『JESUS』のことをもっと知りたい方は、下記のバナーから詳細をご覧ください。
Archive